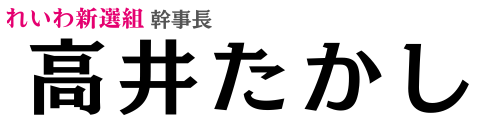【5月13日】政治改革特別委員会/ネット上の真偽を判断する第3者機関を設けるべきでは?

○渡辺委員長
次に、高井崇志君。
○高井委員
れいわ新選組の高井でございます。
私も、法案の審議の前に、一つやはり、先ほども話題に出ましたSNSの誹謗中傷の問題、そしてそれが選挙にも影響を与えるということが、大臣からも、民主主義の危機だと。それは、前から大臣の御持論も聞いていますが、私は、ただ、選挙だけじゃなくてというか、やはりそれ以上に、人の命が実際に奪われる、これは本当に大変なことだと思っています、そこは大臣も認識されていると思いますが。
今、ストーカーの、川崎の事件が、やはり非常に警察の対応が悪かったということで、これは本当に、連日報道されるぐらいの大問題になっていますが、ストーカーで亡くなる人もいますけれども、SNSで亡くなっている人というのは確実に、ストーカーの被害の方より多いと思うんですよね。
そこで、今日、警察に来ていただきました。
別にストーカー被害者とSNSの被害者を比べるわけじゃないんですけれども、まず、実態として、どのくらいの方が現実に亡くなっているかをちゃんと警察は把握しているかという意味で、過去五年間にストーカー被害で亡くなった方の数、それからネットによる誹謗中傷で亡くなった方、これは恐らく自死ということになると思うんですが、その亡くなった数、それぞれ何人か、教えてください。
○大濱政府参考人
お答えいたします。
警察で把握しているものといたしましては、令和二年から令和六年までの過去五年間で、ストーカー事案の検挙状況として、殺人罪を適用したものは四件、被害者の数、亡くなられた方の数は四名でございます。
また、令和二年から令和六年までの過去五年間で、ストーカー被害によって自殺された方、またインターネット上の誹謗中傷等で自殺された方の数につきましては、把握はございません。
○高井委員
総務省は把握されていますか。
○玉田政府参考人
お答えいたします。
インターネット上の誹謗中傷は、短時間で広範に流通、拡散をし、現実の国民生活や社会経済活動にも重大な影響を及ぼし得る深刻な課題であると認識をしております。
お尋ねの、ストーカー被害によって亡くなられた方やインターネット上の誹謗中傷等を理由に亡くなられた方の統計情報につきましては、総務省としては把握をしてございません。
○高井委員
総務省は難しいでしょうね、主管省庁とはいえ。やはり、これは警察ですよ。
必ず、自死された方の場合であっても、警察はやはりいろいろ現場検証したりとか、殺人を疑ったりしていくわけですから、これは自死だと、そのときに原因とかもきちんと把握しているはずなんですよ。だけれども、それをちゃんと残していない、記録に。こういう場で発表できない。
私は、やはり、でも、容易に想像できると思いますけれども、相当な数が。ストーカー被害四名とおっしゃいましたけれども、そんなものじゃとどまらない数がネットの誹謗中傷で亡くなっているのは間違いないと思うんですね。
私は、この間総務委員会で、大臣に、ちょっと私の友人の具体的な事例としてお聞きをしました。
私の友人は事実でないことを書かれて、そのことによって仕事を失いかねない、そして、そのことで本当に精神がおかしくなって、本当に自死も考えるような、そういう、これは誹謗中傷というよりも虚偽の情報なんですよ。偽りの情報をネットに書かれて、でも、そのことによって仕事を奪われかねない。私は、相談を受けて、弁護士とも相談して、削除依頼をしました。しかし、SNSの事業者は、虚偽情報は削除できないと言うんですね。
これは、私は総務省にも相談して、でも、やはり、こういった、明らかに客観的に争いのある情報はしようがないですよ、特に、選挙とかでどっちが事実か分からないなんということはしようがないけれども、明らかに、証明書とかを出してうそだということが分かるものは、やはり削除すべきだし、させるべきだし。
それで、SNS事業者は、裁判してくれと言うんですね。私、弁護士に聞きましたよ、どのくらい費用がかかりますかと。要するに、うその情報ということを証明して、裁判が、仮処分を出すだけでも、費用でも三、四十万、そして期間でも二、三週間かかると言うんです。その前にどんどん拡散されるじゃないですか。だから、こういうものはやはり速やかに、SNS事業者は自分たちで判断できないから、第三者の公正なところで判断してくれ、それが裁判所だと言うんですけれども、裁判所は、余りにもやはり手続とかも難しいし、お金もかかるし。
私は、総務省が、ここはSNSを所管している総務省が、本当に人の命を大切にする村上大臣が決断をして、第三者機関をつくって、そこが、簡易に、しっかり証明書を見せたら、それで事実であるかうそであるかを判定する、それによってSNS事業者が削除する。これをやることで、亡くなる方の数がかなり減ると思いますけれども、大臣、やってくれませんか。
○村上国務大臣
お答えする前に、先ほど斎藤委員の御質問の答弁の中で、最後まで小選挙区を一緒に反対した元島村大臣と言ったんですけれども、御健在でありましたので、誠に私の錯覚で申し訳ありませんでした。大変失礼いたしました。かなり御高齢だったもので、失礼いたしました。
それで、高井委員の問題意識につきましては、総務委員会での質疑を踏まえてよく承知しております。大変難しい問題であると思っております。
しかしながら、Xに掲載された個別の投稿について、削除するかどうかについての適否を判断する立場にはなかなかなり得ない、そういうふうに考えております。
我々のなすべきことは、高井委員御指摘の個別事案も含めたインターネット上の偽・誤情報の流通の実態を踏まえ、どのような政策的対応が必要かについて議論、検討を進めていくことだと考えております。
真偽を判断するための第三者機関を設けるべきとの御指摘につきましては、現在においても、いわゆるファクトチェック機関が活動を行っているものと承知しております。
総務省の有識者会議が昨年九月に公表した取りまとめでは、一つ、プラットフォーム事業者が、情報流通の適正化に取り組む一定の責任を果たすことが求められる中で、ファクトチェック機関との間で緊密に連携、協力すべきことが提言されているとともに、二つ目は、政府、公的機関等からのファクトチェック機関の独立性が確保されるべきだと明記されているものと承知しております。
そういう中で、個別具体的な投稿の削除の要請については、プラットフォームの事業者が自ら定めた削除基準に基づいて適切に判断すべきである、そういうふうに考えております。
総務省としましては、インターネット上の偽・誤情報について、引き続き、表現の自由に十分配慮しながら、総合的な対策を積極的に進めてまいりたい、そのように考えております。
○高井委員
残念ですね。
ファクトチェック機関は確かにあるようで、この間も、各事業者からヒアリングして、例えば、明らかに間違っている情報、東日本大震災は何か人工爆弾で起こされたとか、そういったものについては削除するらしいんですよ。だけれども、そんなことは削除を別にしなくたっていいですよ。そんなのはみんな判断するんですよ、利用者が。
それよりも、こういう私の友人のような、明らかに事実と違って、明らかに証明できるものを、だけれども、ほかの人は分からないから信用するわけですよ。こういったことをやはりやらないと、それをどこがやれるかというのは確かに難しいんだけれども、やはり、事業者の規約が私は不十分だと思うので、それは、もちろん私はXにも言いましたよ、だけれども、なかなか変えてくれないし、そういったことは、私は、総務省の行政指導ででもやるべき、本当は法律にちゃんとそういったことも書いてほしいですけれども、やるべきだし。
とにかく、やはり、法律であったり行政指導であったり、あるいは、私、元総務省なんですけれども、昔は、NTTに対する苦情電話を受けるのが、私、一年生のときの仕事でした。それをNTTに伝えて、やはり、総務省から、監督している部署から伝わると、それは改善してもくれましたよ。でも、今は多分総務省はそんなこともやっていないんですよ。
NTTに対する苦情なんかより、SNSのこの問題は、本当に人の命をなくしかねないことですから、私は、村上大臣は本当に評価しているんです。尊敬しています。自民党の中にあって現職の総理にあれだけ物申した。そして、そういった方が総務大臣になれた。私は、すごいこれは希望の光なんですけれども、でも、このまま、やはり大臣をただやったというだけで終わるんじゃなくて、是非やはり大臣として、一つでも二つでも、足跡、功績を残していただきたい。そしてそれが、私は、このSNS問題は本当に大臣がやるべき仕事。だって、人の命を救えるんですよ。私は、政治家になったのは、一人でも多くの人を救いたい、命を救いたい、これに勝る政治の仕事はないですよ。
大臣、これは本気で、今すぐはできないかもしれないけれども、法改正なり、行政の運用を変えるなり、この問題に本気で取り組んでください。もう一度、大臣、決意をお願いします。
○村上国務大臣
高井委員のお気持ちは分かりますし、お話を聞いている事例につきましてもいろいろ分かりますが、総務省は、裁判機関でもないし、判定できる立場にはないわけなので、それをどういうふうにやるかというのは、これからも皆さん方と考えていくんですが。
例えば、今、オンラインカジノについても、すぐやれとこの間言われて、今、一生懸命検討しているんですけれども、オンラインカジノ一つでも、例えば漫画の海賊版ですら、シャットダウンしたくても、検閲だと言われて止められるわけですよね。
やはり、表現の自由とか言論の自由とか、そういう中で、それに抵触しないようにやるということは、もちろん、高井委員も総務省にいたからお分かりだと思うんですが、我々は、すぐにでもやりたいのはやりたいんだけれども、言論の自由と表現の自由と、どこでちゃんとけじめをつけてやれるかということをきちっとやはり道筋をつけないと、そう安易にできることではない、そういうふうに考えています。
ただ、これは、もうおっしゃるように、非常に重要な問題ですし、だから、この間も申し上げましたように、我々よりも、もっと国民全体が、このままいくと、例えばSNS民主主義になってしまうぞ、それでいいのかということをお互いに考え、議論して、それでまた、SNSでの偽・誤情報をやはりきちっと判断できる見通しを持つということが重要じゃないかと思います。
とにかく、高井委員が評価していただけるのはありがたいんですが、私はスーパーマンでも何でもありませんから、そういう単純なことはできないので、その辺は御理解いただきたいと思います。
○高井委員
だから、第三者機関をつくりましょうと言っているんです、総務省が判断するんじゃなくて。裁判所というのは、やはりそれは逃げですよ。裁判所がそんなのをさばける量じゃないくらいの量がどんどんどんどんあふれ出てきて、だけれども、簡単に証明でき、証明書を一枚持っていくだけなんですから。それをX社は受けてくれないんですよ。だから、どこか第三者機関をつくってこれをやるべきだと。もう私の質疑時間がなくなるので。じゃ、はい。
○村上国務大臣
逆にお伺いしたいのは、第三者機関というのは結構ですが、誰が、どの費用を出して、どういうふうにつくるか、案があったら言ってください。
○高井委員
それを考えるのが総務省じゃないですか、SNSを所管しているんだから。だから、そういう研究会とか立ち上げてくださいよ、早急に。そんなのは国民的理解を得られますから。誰がつくるって、総務省がやるしかないですよ。だから、お願いします。
法案の審議なので、一問だけ聞きますけれども、これは我が党は反対なんです。なぜかといえば、予算をやはりもっと増やさないと。もうこんな、皆さん、漫然と賛成していちゃ駄目ですよ。投票率は全然上がっていないじゃないですか。
投票率を上げるためには、例えば期日前投票、さっきもあったけれども、駅とか大型商業施設とか、そういったところにもっと投票所を増やす、そういった経費を自治体にもっとどんと出すとか、あるいは、投開票の閉める時間だって、自治体に十分な経費が出ていないんじゃないですか。
あと、投開票の時間、夜中の二時、三時まで待たされる。あれだって、もっと人を一気に投入して、それは総務省が予算をけちるから、自治体は対応できないんじゃないですか。
あと、投票率を上げるんだったら、テレビコマーシャルをもっとどんとやるとか、あと、総務省が、政府がスポンサーになって、テレビ番組、一番組買い上げて、ゴールデンタイムに二時間党首討論をやるとか、いっぱい幾らでも考えられるじゃないですか。
投票率向上のために予算を増やすべきだと思いますけれども、いかがですか。
○村上国務大臣
高井委員、総務省を非常に評価していただくのはありがたいんですけれども、総務省も、交付税や特別交付税、いろいろ非常に大変な費用をやって、そういう中でやりくりしているわけですけれども、国政選挙における投票所とか期日前の投票所に要する経費等につきましては、執行経費基準法に基づき、自治体に対して交付することとしております。
投票率については、様々な事情が総合的に影響するため、その状況を一概に申し上げることは困難でありますが、利便性の高い場所への期日前の投票所の設置や投票所への移動支援の取組などの投票しやすい環境の整備のため、必要な予算、人員を確保することは重要だと思います。
一方、投票所等を大幅に増加させるためには、予算だけではなく事務従事者や設置場所が必要であり、それに対して、課題も含め検討していくことが必要となります。
いずれにしても、総務省としては、投票しやすい環境整備につながる取組がなされるよう、必要な予算を確保して頑張りたいと思います。
以上であります。
○渡辺委員長
残念ですが時間ですけれども、一言。
○高井委員
投票率を上げるためにみんなで、みんなで考えましょう。
以上です。ありがとうございました。