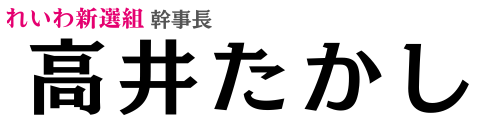【3月26日】財務金融委員会/植田日銀総裁に問う!30年の日本経済が成長しなかった原因は消費税?

○井林委員長
次に、高井崇志君。
○高井委員
れいわ新選組の高井でございます。
今日は、植田日銀総裁、お越しいただきありがとうございます。
実は、私は植田先生の教え子でございまして、大学のときに講義を経済学部で聞いておりました。当時まだ助教授だったんですけれども、新進気鋭の植田助教授のゼミは大人気で私は入れませんでして、もし植田ゼミに入っていたら私の人生もちょっと変わっていたかなと思いながら今日はちょっと質問したいと思います。
是非、日銀総裁の立場ではもちろん来ていただいているんですけれども、やはり経済学の権威、大御所として、是非教え子に答えていただきたいと思います。
まず最初にお聞きしたいのは、これはこの委員会でも何度も私は問うているんですが、この三十年間、日本は経済が成長してこなかった。これは世界中でも本当に日本ぐらいだ。その原因を聞きたいと思います。
我々が主張しているのは、やはり、まず財政出動が全然少なかった。世界各国を見ると、財政出動を増やした国ほど経済成長、GDPの成長率は高くなるという正の相関関係がまさにあって、日本はこの間、僅か一・三七倍、一九九七年から二〇二二年までの二十五年間で僅か一・三七倍しか増やしていません。ほかの国は大体二倍、三倍、あるいはブラジルなんかは十倍以上増やしている。そういったことがまず一つ原因。
それからもう一つは、あの三度にわたる消費税増税です。これは、一回消費税増税しただけで、百年に一度と言われたリーマン・ショックをはるかに上回る消費の落ち込みが起きている。つまり、日本は、百年に一度のリーマン・ショック級の恐慌が四回起きたと同じことだと。消費税増税の影響は極めて大きいと考えていますが、日銀総裁の見解、あるいは経済学の権威である植田先生の見解をお聞きいたします。
○植田参考人
恐縮ですが、本日は日銀総裁としての立場でお話しするということになりますので、財政政策、税制は、政府、国会で議論されるものと考えますので、具体的なコメントは差し控えさせていただければと思います。

その上で申し上げますと、我が国の成長率が九〇年代以降低迷してきた大きな原因としては、理解にすぎませんが、潜在成長率の低下があると思います。そのまた要因として、少子高齢化に伴う労働投入量の減少、あるいはデフレの下で企業が積極的な行動を控えたことで資本ストックの伸び率が低下した、あるいはイノベーションが停滞して生産性の伸び率が低下したことなどもあるというふうに考えます。
また、不良債権問題、相次ぐ自然災害、感染症といった負のショックが短期間に、二十年くらいの間ですが、相次いで発生したことも経済の下押しに作用したと考えております。
○高井委員
事前に、日銀総裁、日銀から、担当者からレクチャーを受けたときも、答えられないんだと。しかし、財政のことの、何か財政をどうするかという質問ではなくて、日本経済が成長しなかった原因として財政出動や増税が関係したんじゃないかというのは、これは別に日銀総裁として答えてもいいと思うんですけれどもね。
まさに、私はよく言っているんですけれども、経済学で植田先生から教えてもらった基本は、これは中学校で習うことですけれども、景気が悪いときには減税をして市中にお金を回し、そして、景気がいいときには過熱を抑えるために増税をしていく。まさに、税は財源だということばかり、皆さん、国会議員の人は多く考えるんですけれども、財源であると同時にこういう景気の調整機能があるわけでございますから、これは答えていただいてもいいと思うんですが。
改めて、日銀総裁としてで結構ですので、財政出動や消費税の、消費税というか、減税をしてこなかった、そういった影響がやはり一定はあるということはお認めいただけませんか。
○植田参考人
一般論として、財政政策に景気調整機能があるということはおっしゃるとおりだと思いますが、具体的にどの局面でどう働いたかということに関するコメントは差し控えさせていただければと思います。
○高井委員
ありがとうございます。
一般論でも、まさに財源調整機能がある、景気を調整するビルトインスタビライザーという機能があるわけで、そこをやはり、もっと国会は、あるいは政府は、あるいは財務省は真剣に考えていただきたいと思います。貴重な答弁をありがとうございます。
ただ、減税するべきだ、あるいは財政出動するべきだというときに、やはり問題になるのは国債発行残高、日本の財政がもうこれ以上は国債発行できないんじゃないかということで、よく財務省やあるいはほかの皆さんも言われるのは、債務残高が日本は一番最悪の水準なんだと。確かに、これはG7で比較すると七位なんですね。
しかし一方で、ほかの指標を見れば、非常に重要な政府の純利払い費のGDPの比率というのは二番目にいいんですよ。あの財政優等生のドイツよりもいいんですね。そういったほかの指標も、対外純資産対GDP比なんかは一位、それから一般政府対外債務比率も一位、こういう、G7の中でもトップクラスでいい。
これはやはり、確かに負債は大きいけれども国の資産はある、個人金融資産だけでも二千二百兆円ある、こういったことが原因で、それが市場の評価となって、CDS、クレジット・デフォルト・スワップで算出した五年以内に日本国債がデフォルトする確率というのは僅か〇・二三%、これもドイツに次いで低いんです。ちなみにイタリアなんか二・四%ですし、トルコなんか一〇%を超えている。
こういう状況なわけですから、私は、日銀は国債を半分引き受けている、持っているわけですから、こういった状況を加味すれば、日銀がそれだけ国債を持っていても、これは日銀にとって何の問題もないんじゃないか、こういう聞き方をすれば日銀総裁としても答えられると思うので、日銀として問題ないと思いますが、いかがですか。
○植田参考人
ちょっと質問の御趣旨を理解しているかどうか。財政に問題が生じて長期金利が上がっても、日銀の財務に問題があるかどうかという御質問でしょうか。
先ほどと同じですが、財政破綻という仮定の質問に直接お答えすることは適当ではないと思います。
ただ、長期金利が上昇したときに、国債を保有している日本銀行の財務への影響はどうかということで申し上げるといたしますと、私ども日本銀行では、保有国債の会計原則について、会計方法、評価方法につきまして、私どもの財務の特性や保有の実態等を踏まえて、いわゆる償却原価法を採用しております。このため、評価損が発生、拡大したとしても、期間損益には影響しないという構造になっております。
○高井委員
日銀が答えられる範囲で日銀としてどうかという質問に限らせていただきましたので、日銀としては財務上何の問題もないという御回答でしたので、はい、それを受け止めたいと思います。