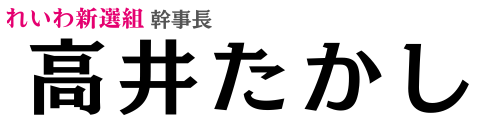【3月17日】政治改革特別委員会/企業からの献金の禁止は憲法違反?(参考人質問)

○高井委員
れいわ新選組の高井崇志です。
今日は、貴重な御提案、ありがとうございます。
さっき国民民主党の長友委員から、憲法との関係について四名の先生に質問がありました。私も四人の先生方に同じ質問を最初に聞きたいと思うんですが、同じ憲法の話なんですが、もう少し踏み込んで。
私たちれいわ新選組は、今、企業・団体献金禁止の憲法違反から、さらに政治団体まで全てこれを禁止してしまうのは、これはやはり行き過ぎで、憲法違反の疑いがあるんじゃないかということで、立憲さん、それから維新さんはそこを除くという法案を出してこられました。 ただ、我々は、実際は結構、企業やそれから労働組合などの隠れみののような形で政治団体がつくられて、脱法的に行われるんじゃないかということで、これはもう全面禁止した方がいいんじゃないかという意見です。
そこについてはもし意見があればお聞きしたいんですが、更に私が聞きたいのは、これを内閣法制局に問うても全く回答が返ってこない。衆議院法制局はもちろん見解を述べていただいたんですが、有権解釈権はないんだとおっしゃって、あくまでも立法の補助であるということです。
それから、内閣法制局は、この問題はもう三十年前から、この企業・団体献金が憲法違反かという議論があるのに、全く何の見解も持っていないと。先日、総理が答弁したら慌てて、しかもいまだに、今後検討するとか、具体的な事例に応じて検討すると。これは私は、ちょっと内閣法制局の怠慢、あるいは、その設置法に問題があるのであれば、これはやはり変えないといけないんじゃないか。 やはり、こういうおよそ法律の運用に対して、内閣法制局というまさに法律のエキスパートが集まったあれだけの組織をつくっておきながら、政府から聞かれたことにしか答えない、政府の法律にしか答えないというのはもったいなさ過ぎる。 これは全部最高裁まで一々裁判するのかということであれば、やはりもうちょっと、国民から、少なくとも国会からの要請に対して速やかに憲法解釈を述べる、そういう機関であるべきだと思っていますが、それぞれ先生方の御見解をお聞かせください。
○中北参考人
お答え申し上げます。ちょっと前段の御質問から入らせていただきたいと思います。
私は、二〇一九年、れいわ新選組が、個人献金を集めて、千円から握った方々の献金を受けて、そうした形で活動を始めたということを高く評価しているものであります。
しかし、その一方で、企業・団体献金、さらには政治団体からの献金を禁止するというのは、政治活動の自由上、やはりこれはさすがに行き過ぎではなかろうかというふうに考える次第であります。冷静に、何が問題なのか、どういう弊害があるか、こういったところ等を勘案して結論を出していただきたいと思います。
二点目の憲法の解釈の問題でございますけれども、日本は三権分立でございます。有権解釈というのは基本的に、最高裁においてなされる、裁判を通じてなされるという形になっております。そういうことから、内閣法制局はそういう立場を取っている、このように理解しております。
したがって、もしこうしたことを避ける、憲法解釈ということをきちんと、より積極的に受け取れるようにするのであれば、維新さんが主張しているような憲法裁判所を設置するとか、こういったことも含めて考えるべきであって、しかし、三権分立ということを考えると、軽々に内閣法制局に有権解釈を求めるような制度を導入していくというのが正しいかどうか、これは慎重たるべき、このように考えております。
以上です。
○成田参考人
企業、団体に政治団体も含めて、政治団体も献金を禁止するという考え方がございます。しかし、憲法には二十一条に結社の自由というのがございまして、個人だったら献金できるけれども、結社にしたら献金できなくなるといと、結社の自由の侵害ですよね。結社の自由というのは、結社をつくる自由と、つくられた結社が活動する自由がございます。もちろん企業も労働組合も結社の一部ですから、結社の中にも一部、その特性に応じて献金を禁止することは構いませんが、結社は全て献金できないとなると結社の自由の明白な侵害になるということで、内閣法制局も衆議院法制局もうんとは言わないということだろうと思います。
それから、政治団体をつくると抜け道になるという話が何回か出ておりますが、西松事件というのがございまして、政治団体をつくって迂回の献金をして事件になったのがございました。小沢先生だけじゃなくて、自民党、幹事長が、ちょっと名が出てきませんが、大量に摘発されました。
西松事件がございますから、ですから、そういうことをやればそれは取締りの対象になるということで、そこの手当ては現在既にできているということだろうと思います。
○小林参考人
まず有権解釈の話ですけれども、正確には、三権分立ですから、最高裁にも内閣にも国会にも解釈権があるんですね。つまり、分かりやすく言うと、自衛隊法を国会が作ったということは、あの自衛隊法は合憲であるという国会の判断が出ているんです。違憲だったらやるわけないじゃないですか。たまたまそれが事件になって最高裁に行ったときに、最高裁の有権判断が出る。それが矛盾したらどうするか。それは立法と最高裁で調整されていく。これが歴史です。ですから、有権解釈という点でいけば、先ほど話にも出ましたけれども、内閣は内閣法制局、衆議院にも衆議院の法制局があるじゃないですか。参議院にも参議院の法制局があるじゃないですか。まずそこから意見を徴して、それを国会の多数決で我々はこれに賛成すると言えば、国会による、国権の最高機関ですからね、有権解釈が立ちます。それは一つの政治的議論のガイドラインになると思います。
それから、今、成田先生がおっしゃったんですけれども、憲法二十一条で結社の自由と言いますけれども、各政党を見ても、何となく意見の合う人がまとまって動くのが人間の本質じゃないですか。そういう意味で、政党というのは自然発生でできる。これが結社の自由ですよ。
ただ、さっき中北先生が、部分利益であっても全体利益と調整してと巧みにおっしゃったけれども、部分利益しか目指していないものが、その利益を目指して金で権力者と取引する、これがトラブルを起こしている事実がいけないと言っているので。部分利益しか持っていない会社が、発言する自由はあるんですよ、金で買う自由はなくても、表現の自由はあるんですから。それは私も禁止していません。
だから、その点を少し整理して、そういう意味で、企業と労働組合などの団体の政治献金は禁止すべき方向性にある、だけれども、政治結社の献金は自由の方向性にあると思います。
○谷口参考人
後段部分につきましては、現行制度を取る限りにおいては、過日の内閣法制局長官のような答弁にならざるを得ないかというふうに存じます。
それから前段部分につきまして、政治団体から政党その他の政治団体等への寄附を禁止いたしますと、そもそも合憲性の問題が生じるとともに、当該政治団体がアメリカのスーパーPACのようになるおそれが生じます。スーパーPACと申しますのは、候補者に献金をすることはできませんけれども、個人や企業、団体からは無制限にお金を集められて、その莫大な金銭を、候補者のいわば別働隊としてテレビ広告やネット広告に投入をしている。これがアメリカで政治資金が非常に多額になっている元凶ということでございます。
このスーパーPACとして機能するその他の政治団体は、これはあくまで政党外部の存在でありますから、その党が一年に幾ら政治資金を使ったのかという集計の中には当然入ってまいりません。また、相互に独立をして動くという建前ですから、もし隠そうとすれば、その合算も容易ではないわけでございます。これを勝手連といえば聞こえがよくなるわけでございますが、言葉を換えて政治資金版二馬力選挙というふうに申し上げれば、この潜在的な危うさを御理解いただけるかと存じます。
○高井委員
ありがとうございます。大変勉強になる御意見、たくさんありがとうございました。
それでは、もう一つ、これも四人の参考人にそれぞれお聞きしたいんですが、先ほど中北参考人から、れいわ新選組の個人献金、一生懸命集めて、褒めていただきましたが、正直、もう限界がやはりあります、個人献金。我々はやはり常に資金不足でございまして、そういう意味では、この企業・団体献金も本当はという部分はありますが、ただ、やはり政策をゆがめるところが非常に問題であると我々は考えていますので、全面禁止をあえてここはしております。そういった中で、私の提案は、常々国会で申し上げているんですけれども、政党交付金を見直していただきたい。今の政党交付金は議席数割で全部配分をしていますが、しかし、少数政党、例えばイギリスなんかは、ショートマネーといって野党にだけ配分される政党交付金がありますし、それからあとは、半分は均等割にして、そして残りは得票数割にするとか、そういう方法があると思うんですね。というのは、今回だって、我々、小さな政党ですけれども、こうやって同じ時間をいただいて十五分質疑させていただいていますし、あらゆる法案について必ず賛否をしっかり調査をした上で行っていますから、そういう共通機能が各政党にあるわけで、これは議員数で割ったら、明らかにやはりその配分として私はおかしいと思いますので、政党交付金について、中北先生や谷口先生は言及もありましたが、四人の先生からそれぞれ、政党交付金、今私が申したような少数野党にも厚く配分するという方法はどうお考えでしょうか。
○中北参考人
お答え申し上げます。
政党交付金を使って様々な施策、特に民主主義を促進する方向で効果を考えていくということは私は有益だと思いまして、その一環として、女性議員を増やす、こうした方向で使う女性議員割、こういったことを考えてはどうかということを御提案させていただきました。
そういう観点からいえば、確かに少数政党を優遇するということはあり得るかもしれませんけれども、そうなると、例えば国会に議席がない政党との平等をどうするのかといった問題がかなり強い形で出てくるのではないかというふうに考えますし、しばしば野党の先生方は、イギリスの制度がすばらしい、野党に傾斜して配分されるのがすばらしいとおっしゃいますけれども、イギリスのこうした助成金の金額、規模というのは日本の十分の一ぐらいでございまして、もしそうしたら、恐らく野党への配分額というのは減ってしまうのではないか、このように考えます。
全体を見て、これだけの多額の政党助成があるのは日本とドイツです。ドイツの場合は、やはり闘う民主主義ということで、戦前のナチズム、こういったものの反省から、政党法を作りながら政党助成をしていく、こういう形になっていますけれども、日本の場合はそういう形にもなっていない。ですから、全体を見て検討しなければ相当危ういことになるんじゃないか、このように考えております。
以上です。
○成田参考人
先ほど冒頭発言で御紹介しましたが、平成五年の社会党と公明党の共同提案による政党助成金交付法案は、議席は考慮せず、得票率のみで配分するという規定になっておりました。その理由は、国民が寄附をする代わりに税金から払ってもらうんだから、国民の支持を正確に反映する配分方法が望ましい、それは得票率であると。議席というのは小選挙区が入るとゆがむから、その議席でゆがんだ比率で各党に配分するのはおかしいということで、社会党、公明党案は得票率による配分をやっていました。
一つの考え方であろうというふうに思っております。
○小林参考人
やはり、一人一票を前提とする民主主義ですから、得票率に比例するのがいいと思います。
ただ、確かに、れいわみたいに、具体的例を言って申し訳ないけれども、有為な新政党がありますよね。そういうものを芽を摘まないためには、まるでベーシックインカムみたいに全ての政党に基本的に一塊上げた上で、あとは得票比例でいく、これが一つ。それからもう一つ、議院内閣制を活性化するために、よく言われることですけれども、野党第一党のシャドーキャビネットにちゃんとした経費を支給する。これでも随分政党の活性化はできるんじゃないでしょうか。
以上です。
○谷口参考人
御趣旨に反対ではございませんけれども、なかなか合意可能性がないかなというふうに考えております。
それゆえに、私は、政党交付金基金というものを設けて、国民の懐を痛めることなく、寄附というような形で政党交付金の増額を図る、当然これは与党にも野党にも益するところがあるのではないかというふうに考えておる次第でございます。
○高井委員
大変貴重な意見、ありがとうございました。
これで終わります。ありがとうございます。