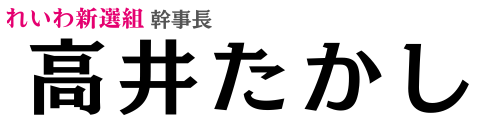【5月9日】衆議院・財務金融委員会/消費税について「食料品ゼロ」で飲食店は負担増の可能性が指摘されているが大丈夫か?「社会保障の財源」は本当か?

○井林委員長
質疑の申出がありますので、順次これを許します。高井崇志君。
○高井委員
れいわ新選組の高井でございます。
今日はちょっと、厚生労働委員会でも質疑に立つものですから、あと、途中、政治改革特委もあって三つかけ持ちで、少数政党なので、済みません、順番を変えていただきまして、誠にありがとうございます。
消費税についてお聞きしたいと思いますが、れいわ新選組は、結党以来、消費税廃止を一貫して訴えてまいりました。六年前に山本太郎代表が訴えたときは本当にたった一人で、ほかの党に見向きもされなかったわけですけれども、今や消費税減税が大勢を占めるに至っている。
野党各党も、さきの衆議院選挙では、立憲民主党を除いて全党が公約に掲げた。そして、立憲民主党もようやく減税というのを打ち出していただいた。そして、与党も、公明党は、はっきり言っていませんけれども、消費税減税の方向。そして自民党も、参議院の八割が、アンケートに、減税が必要だ。そして先日は、六十九名の議連のメンバーが、首相にもこれを、主張しているということで、国会議員の大勢が消費税減税となる中で、そして国民の皆さんも、先日の産経新聞、FNNの調査によれば、賛成が六八%ということで、本当に国民それから国会議員のほとんどが求めているのに、自民党のごく一部の執行部の皆さんだけが反対をしていて、先ほどの報道によれば、昨日、総理と森山幹事長が会談をして、消費税減税は見送ると政府高官が明らかにしたということですから、当然、加藤大臣も御承知かと思いますけれども。
本当に消費税減税は検討すらしないんですか。こんなことで本当に自民党は大丈夫ですか。政府は大丈夫ですか。大臣、消費税減税、やらないんですか。
○加藤国務大臣
政府におけるということで答弁をさせていただきますと、消費税については、急速な高齢化などに伴い、社会保障給付費が大きく増加する中において、全世代型社会保障制度を支える重要な財源と位置づけられていることから、政府としてはその引下げを行うことは適当でないと考えておりますし、従来からもそう答弁させていただいているところでございます。
○高井委員
報道では、政府高官も明らかにしたということですから、政府も含めて、与党としてそういう決断をしたというふうに報道では読めますよね。
本当に今の国民の皆さんの暮らし、元々、三十年デフレ不況が続いて、そこにコロナが来て、そして物価高ですよ。今の物価高は、じゃ、経済成長にデフレ不況が克服されたといえば、そうではない。コストプッシュインフレですよ。米の値上がりを始め、あるいはエネルギー価格の値上がりなどで本当に悪性のインフレがある中で、やはり今一番必要なのは、消費税廃止、それから現金給付、それから社会保険料の減免、これを我々は国債を財源でやるべきだと。これについては来週の予算委員会で私、また取り上げますので、今日は少し各論というかですね。
我々野党は、消費税減税で、我々は廃止ですけれども、そこは百歩譲って、まず第一歩ということで減税でもまとまればと思っているんですけれども、なかなか野党がこれまたばらばらで、現在まとまっていません。是非ここは野党第一党の皆さんに懐深く、野党がまとまれば、今、少数与党ですから、法案は通るんですよ、衆議院で。消費税減税法案を衆議院で通して、そして、参議院では否決されたって、そうしたら、いよいよそれはもう内閣不信任案ですよ。内閣不信任案を出して、そしてそれを可決して、解散・総選挙はまさに消費税解散、そうすれば政権交代間違いなしだ、こういうシナリオが明確に浮かぶわけで、ここは是非、それをやるためには野党がまとまる必要があって、野党第一党に私は懐深く対応していただきたいと思います。
今、野党第一党の立憲民主党の案というのは、食料品ゼロ、あと、一年だけというのも、これも大いに不満ですが、ここは協議の余地がある、延長の可能性もあるということですが、食料品ゼロが、やはり問題点が幾つかあると思いますので、ここは政府にも聞いておきたいと思います。
大臣にお聞きしますが、確かに、食料品ゼロにすべきというのが世論調査でも一番多いですね、三五%、国民の支持も得ている。ただ、なかなか、国民の皆さんは、食料品ゼロになったときにどういう問題点があるかということは、ほとんどの方が知らないと思うので。
単に、食料品、今八%の軽減税率がゼロになれば、それは八%値下げになればいいなと思っているとは思うんですけれども、しかし、残念ながら、食料品というのは、結構、スーパーなんかに行けば分かるとおり、日々刻々、特に生鮮食料品なんかは日々刻々値段が変わって、それはやはり、市場や競りで決まったり、天候の影響で収穫量が変わったり、あるいは、生鮮食料品じゃなくても、例えば、輸入品であれば為替の影響も受けるし、それから、エネルギー価格の影響によって値段も変わっていく。こういったものが、消費者の皆さんは、消費税というのは何か事業者が原価を決めていて、価格を決めて、そこにプラスで八%明確に乗っていると勘違い、これは勘違いなんですよ。
消費税というのは、法律上明確に、事業者が決めると。事業者に課される税ですから、事業者が消費税分も込みで値段を決めていて、そのことは財務省も、消費者が支払うことを予定しているとしか何度聞いても答えないわけですよ。予定ですから、別にそれを必ず乗せなきゃいけないという義務は事業者にないわけですから、その消費税分の予定している、消費者が払う分も予定している分も含めて事業者が決めているだけですから、私は、これは、消費税八%をゼロにしても八%そのまま下がるということはないと思いますけれども、大臣はどうお考えですか。
○加藤国務大臣
繰り返しになりますけれども、政府としては食料品を含めて消費税率の引下げをすることは適当でないと考えているところでございますので、その上に立って、今の御質問ですから、あえてお答えさせていただきますけれども、食料品に係る消費税率を変更した場合の販売価格については、基本的には消費税率の変更分が価格転嫁されると認識をしておりますが、他方で、今委員からお話がありましたように、特に、日々価格が、仕入れ値ですかね、が動くようなもの等、あるいは需要が変化といった様々な要素を踏まえて、最終的には事業者自身の経営判断に基づいて価格が決定されるという一面があることはそのとおりでございますので、実際どうなるかについて確たることを申し上げることはできないということでございます。
○高井委員
今はっきり認めていただきましたように、事業者の判断で決めていいんですよ、法律上そうなっていますからね。なので、消費税分を消費者が払うことを予定しながら、事業者が最後は、やはり、この値段で買ってくれないと売ってもしようがないわけですから、あと、競争相手もいるわけですから、そういう意味では、事業者が、まあ今も本当にぎりぎりの中で消費税を転嫁できずに苦しんでいる事業者はいっぱいいると思うんですね。そうなると、食料品の値段が、もしゼロにしても下がらないとなった場合、一番打撃を受けるのは飲食店なんですね。飲食店は食料品を仕入れていますから、仕入れているときに、今は、仕入れ値の一〇%を控除できるんですね、仕入れ税額控除といって、控除できる分、楽なんですけれども、今度、ゼロになったら控除できなくなりますから。
ただ、立憲民主党さんとか維新の方は、いや、その分値段が下がるだろう、下がるんだから仕入れ税額控除ができなくたって同じじゃないかと言うんですけれども、今申し上げたとおり、下がらなかったとしたら、これは食料品店にとっては間違いなく増税になると思いますけれども、大臣、いかがですか。
○加藤国務大臣
食料品店。飲食店だというふうに思います、今のお話は。
まずは、先ほどから申し上げておりますように、引下げは適当でないということを前提にお話をさせていただきますが、食料品の税率をゼロとした場合の飲食店が受ける具体的な影響、これは、委員からも今お話があった、様々な要素が関係するため確たることは申し上げられませんが、ただ、食料品だけの税率を下げるとすれば、外食は課税されているわけですから、基本的に、外食と食料品との税率の差、これは大きくなるということは言えると思います。
○高井委員
おっしゃるとおり。私は今言わなかったんですけれども、大臣からあえて言ってもらいました、外食の場合を。だから外食するのを控えるという方も当然増えるだろうということで、飲食店にとっては非常に打撃が大きい。もう既に飲食店の方からかなりの悲鳴の声が上がっていますので。
私は、立憲民主党さんには敬意を表します。あれだけ頑固だった野田代表を説得していただいて消費税減税にかじを切ったことはありがたいんですけれども、ここはもう一歩、野党がみんなでまとまるために。既に三年前に末松さんが御努力いただいて、消費税五%、一律減税法案、そしてそうすればインボイスも廃止につながるということで、そういう法案を三年前に出しているんですよ。今の立憲民主党の小川幹事長が筆頭提出者ですからね。この法律を是非皆さんで、野党が一致結束してこれを出して、そしてさっき言ったように衆議院で通せばこれは実現するわけですから、是非野党第一党の皆さんには懐の深い判断をお願いしたいと思います。
ちょっともう時間がなくなってきたので、ちょっと飛ばしまして、社会保障の財源かどうかということ、最後に通告、質問しようと思っていたことなんですけれども。
これは、実は神野先生、加藤大臣もよく御存知だと思いますが、私も大学で、教え子の一人なんですが、神野先生がこう言っています。政府の税制調査会の委員もした後、地方財政審議会の会長もされたまさに政府の重鎮ですけれども、社会保障負担を付加価値税、日本でいえば消費税ですね、と結びつけようという考え方は日本以外ないと。これは江田憲司さんもよく言っていますけれども、世界中で社会保障の財源にしている国はないんですね。
私は、かつて、今の社会保障の財源にしたのは二〇一一年、一二年、税と社会保障の一体改革のときに無理やりこじつけて社会保障の財源にしましたけれども、それ以前は、財務省のそういう審議会や有識者会議でも、ヨーロッパではそういう考え方はない、やはり消費税というのは社会保障の財源としては不向きなんだ、だからヨーロッパで付加価値税を社会保障の財源にしている国はないというふうにはっきり財務省も言っていたのに、政治に押し切られたのか、無理やり、社会保障の財源だ。まあその方が国民にとっては聞こえがいいからそういうふうにしていますが、しかし、これは前も指摘しましたけれども、特定財源じゃないですから、一般財源なんですから、お金に色はありませんから、もういいかげん、社会保障の財源だと言い張る、法律のお題目を唱えるのはいいんですけれども、現実的にはそうではないということを財務大臣にはお認めいただきたいんですけれども、いかがですか。
○加藤国務大臣
済みません、私も神野先生は大変敬愛しているところでございますが、ただ、具体的にどういう発言されているかは承知していないので、それには答弁を控えさせていただきたいと思いますけれども、我が国においては、少子高齢化が急速に進展し、高齢化率が世界で最も高い水準となる中で、国民全てが人生の様々な段階で受益者となり得る社会保障を支える経費は、国民全体が皆で分かち合うべきとの理念の下、現役世代だけでなく幅広い世代が負担する消費税を充てるのがふさわしいという考え方に立ち、社会保障・税の一体改革において、消費税を社会保障目的税化したところであります。
また、消費税収については、制度として確立した年金、医療、介護、少子化対策の社会保障四経費に充てること、これは消費税法に規定をされているところでございまして、それにのっとって財政を運営させていただいているところでございます。
○高井委員
それは、社会保障額の方が圧倒的に大きいわけですよ。今、消費税は二十四兆、五兆ですかね。それ以上にはるかに大きい社会保障額があるんだから、それはそういうことにしておけば確かに済むんですけれども、そもそもの税の考え方として、やはり消費税というのは、付加価値税というのは社会保障には不向きでありますし、だったら、例えば消費税を上げ下げしたら社会保障の金額が変わるんですか。変わるわけないですよね。社会保障の額はもう決まっているわけですから、それに消費税をただ充てているだけだということを、是非これは国民の皆さんが広く知っていただきたいと思います。
では、最後にもう一問。
これは局長で結構ですが、ちょっと順番を飛ばしちゃったんですけれども、さっきの食料品ゼロと同じ考え方なんです。実は輸出還付金、それから、私はこの委員会でも、人件費にも課税をされているんだからそこは、しかし財務省の答えは、輸出還付金も人件費も事業者が、相手方がその分値段を下げているんだからとんとんでしょうということですけれども、さっきの食料品と一緒で、値段が下げられない。輸出還付金だって、下請事業者が値を下げられないというケースがあるわけです。こういったケースについてはいずれも、これは財務省の答弁は現実を把握してない。要するに、値段が下げられないということを理解していない机上の空論だと考えますが、財務省、いかがですか。
○井林委員長
青木主税局長、手短にお願いします。
○青木政府参考人
まさに消費税の転嫁の問題だと思いますが、令和五年七月に行われました中小企業庁の転嫁状況に関するサンプル調査におきまして、価格に転嫁できたと回答した割合は九二%となっておりますので、基本的に消費税は転嫁できているものというふうに認識をしております。
○高井委員
そんな調査に正直に答えないし、さっきも大臣から答弁いただいたように、消費税を込みで、もうあとは事業者が決めているわけですから、そういうのは全くの机上の空論だということを申し上げて、質問を終わります。
ありがとうございます。