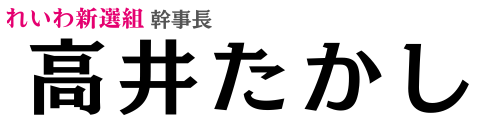【3月24日】政治改革特別委員会/自民党と内閣法制局に問う!企業献金は営利企業にとっては背任・贈賄行為では?

○渡辺委員長
次に、高井崇志君。
○高井委員
れいわ新選組の高井でございます。
質問に入る前に、先ほどから三月三十一日にこだわるかという話があります。私はこだわる必要はないという、今日の理事会でも申し上げましたが。ずるずるいたずらに何週間も延ばすとかは論外でありますけれども、先ほどまさに公明党さんから口頭で国民民主党との合意の案が出て、でも、いつ法文になって出てくるのかよく分かりませんし。自民党さんは、齋藤筆頭理事は今いなくなりましたけれども、先週、立憲民主党と維新が修正協議をしてまとめたものが水曜日には出てきたのに、水曜日にお経読みをやって金曜日に審議すればいいじゃないですか。それをやらないで、国会の慣例だからとかいって、まずは理事懇をやって、金曜日にお経読みだけをするとかね。真面目に三月三十一日でまとめようなんという態度には到底思えないです。
引き延ばせば結局全員通らなくて今のまま、これが自民党にとっては一番いいんじゃないですか。だから三月三十一日でお尻を切って、はい、まとまりませんでした、これで終わりですというのを目指しているとしか思えませんから。私は、せっかく公明党と国民民主党から案が出てきたので、しっかりこれを協議して、くだらない国会の慣例にとらわれないで、しっかり委員会を毎日でも開いて合意を得る努力をすべきだと。
さっき小泉委員が委員会の権威に関わるなんて発言をしましたけれども、委員会の権威なんかより国民の皆さんの思い、何としても企業・団体献金禁止で合意してほしいと。それを我々は最大限やるべきだということを申し上げて、質問に入ります。一問目は小泉委員に聞きますから、もし答えたければ、この質問と併せて答えてください。
自民党さんに聞きますが、前回の参考人質疑で、小林参考人、先ほど維新の青柳さんからも指摘がありましたけれども、非常に重要な、私は全く我が意を得たり、同感だと思った発言があります。それは、株式会社は営利法人であるから、役員が営利に結びつかない献金を行ったら、その本質は法人に対する背任であり、逆にそれが営利に結びつくならばそれは贈賄であろう、権力による決定を金で買うような献金は買収以外の何物でもないと。私はまさにここが企業・団体献金を禁止する本質的な部分だと思いますが、自民党さん、これに対して反論はありますか。
○小泉(進)議員
まず、御質問にお答えをする前に、齋藤筆頭の名誉を守るためにもここは言わせていただかなければいけないと思うんですが、この委員会運営において齋藤筆頭があたかも修正案について審議を延ばしたということは、高井先生、これは事実とは違います。
まず、この委員会の委員長は立憲でありますし、我々は多数を持っていない自民党であります。そういった中で、野党の落合筆頭、今日は自民党席に、私の席に座っていただいておりますが、ありがとうございます。そういった中で、まさに落合筆頭から示された日程で真摯に齋藤筆頭は議論をされて決まっています。そして、こんな委員会の申合せよりも国民の方が大事だと言いますが、我々は国民の皆さんに選ばれて、そして委員会で与野党で合意に基づいて三月三十一日までとやっておりますので、私はその中で議論をして進めることが大事なことだと思っております。
その上で、今の御質問で、企業の献金というのは結果としては背任じゃないかという小林参考人の言葉を引いて反論があればということですが、私は、背任という指摘については、例えば会社においては営利に結びつかない慈善団体への寄附を行うことは社会貢献活動の一環として認められていると思います。また、贈収賄という指摘については、参考人質疑において中北参考人から、企業だって被災地に寄附することがある、狭い利益だけでやっているわけではない、様々な広い利益で行動することも当然行っているわけでありますと述べられているとおり、企業は公益的な観点からの様々な活動も行っています。
これを単純に、本質において買収だとか、露骨に公共の福祉に反すると評価することは、企業やその構成員、従業員の皆様方の活動を不当におとしめるものだと思います。御指摘の見解は企業活動の実態を極めて単純な図式で分析したもので、具体的な政策の制度設計には堪え得る見解ではないと考えております。
○高井委員
小林先生の見解をそこまでおっしゃるかと。ちょっと、参考人に対する敬意を欠いているのではないかと言わせていただきたいと思います。
それから、さっきの齋藤筆頭の件は、修正案が出てくるのが遅い、その前に審議をしてきたのに今頃出してきてというような発言を理事会でされているんですね。ですけれども、修正協議というのはそういうものじゃないですか。これからも、国民民主党と公明党のだって今出てきたわけですし、これからの国会の熟議の在り方というのは、こうやって委員会で議論をして、お互いが歩み寄ったら修正をして、そこで審議時間が足りないのであれば延長して審議する。これが全くもって国会のあるべき姿だということを申し上げて、質問に移ります。
内閣法制局に今日はまた来ていただいていますけれども、これはなかなか内閣法制局に個別に聞いても答えてくれないんですが、一般論で結構です。一般論で、れいわ新選組が今こだわっているのは、政治団体が献金することは憲法違反になる疑いがあるということを立憲民主党、維新を始め野党五党は言っているわけですけれども、本当にそう考えるのか。内閣法制局の見解を教えてください。
○佐藤政府参考人
お答え申し上げます。
ただいまの御質問につきまして、一般論としてのお答えになりますが、企業・団体献金の禁止、政治団体からの献金の禁止ということについて、まず前提として、政治活動の自由につきましては、憲法第二十一条第一項に規定する集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由の保障に含まれるものと解されており、一方で、公共の福祉の観点から必要やむを得ない限度において一定の制約に服すべき場合があると考えられます。
企業、団体が政治活動に関する寄附を行うことにつきましては、政治活動の自由の一部であり、その制約に関して公共の福祉の観点からの必要やむを得ない限度のものとしてどのようなものが許されるか、これにつきましては、私ども行政府におきまして、閣議に付される法律案の審査などを所掌する内閣法制局として具体的に検討はしておらず、また、企業・団体献金の禁止の在り方を含め政治資金規正法の改正について、まさに各党各会派において御検討の上、国会に法律案が提出され、この委員会におきまして議論がなされているものと承知しておりまして、その法案の内容に関わる事柄についてこれ以上お答えすることは困難であると考えております。
○高井委員
今聞いたのは、政治団体はと聞いたんですよ。今の答えは企業・団体献金の禁止ですよね。政治団体が禁止されることについてはどうお考えですか。
○佐藤政府参考人
私、確かにただいま企業、団体がと申しました。ただ、政治団体も団体ということであれば、団体という性格は持つものと考えます。その上で、繰り返しになりますが、その制約に関して公共の福祉の観点からの必要やむを得ない限度のものとしてどういうものが考えられるか、そういうことについての検討が必要ではないかということでお答え申し上げました。
○高井委員
今争点になっているのは政治団体を除くというね、政治団体の寄附が憲法違反かどうかということをこの国会でも何度も議論しているのに、内閣法制局は政府が出すものにしか見解を出さないと。この間の参考人質疑でも参考人の方が憲法裁判所でもつくるしかないとおっしゃっていましたけれども、私もそうかなと思ってしまいますよ、今のような答弁をされると。だけれども、憲法裁判所をつくらなきゃできないことなんですかね。しかも、総務省が、法律ができたら運用は総務省がやるわけでしょう。議員立法だろうが、政府提出法案だろうが法律を所管するのは総務省になるわけで、そのときにできた法律が憲法違反だったらどうするんですか。それに対して内閣法制局が事前に見解を述べるということは当たり前のことで、全く去年の国会から述べていませんけれども、私は法制局の姿勢に対しては非常に憤りを感じます。
本当に法制局設置法の改正が必要なのであれば、そこを改正してでも、あらゆる法律について内閣法制局がきちんと見解を、特に憲法との関係を聞かれているわけですから、そんなの簡単に国会議員とかは答えられませんよ。もちろん衆議院法制局が頑張っていろいろな見解を出してくれていますけれども、それに対してこの委員会で我々としては内閣法制局の見解を聞いているわけですから、是非そういった姿勢は改めていただきたいと申し上げておきます。 それでは、衆議院法制局にも今日は来ていただいていますので、具体的なことをこれ以上内閣法制局に聞いても答えませんから。政治団体による寄附の禁止が憲法違反の疑いがあるということは事前に聞いています。ですが、金額の目安はあるんでしょうか。維新の会は最初に一千万円が憲法上できるぎりぎりの案だと言って出してきたけれども、今、二千万に後退しています、譲歩しています。金額の目安はあるんですか、衆議院法制局、お答えください。
○神﨑法制局参事
お答え申し上げます。
まず前提として、私ども衆議院法制局は、与野党問わずに御依頼に基づいて、その会派の先生方のお立場に立って条文案を立案することを職責とする国会の補佐機関でございます。立案に当たって憲法問題を始めとする法解釈に関して御助言申し上げることはございますが、あくまでも各会派のお立場に立った上での解釈について申し上げているのであり、私どもに有権解釈権はございません。この点を御理解いただきたいと思います。 その上で、一般論として上限額についてお尋ねでございましたが、上限額について、当然、立法事実を踏まえて合理的に設定しなければならない、これは言うまでもないことでございます。
では、その上で具体的な金額として幾らが妥当かということにつきましては、一方では立法事実に基づいて弊害防止のために必要最小限度の金額とすること、他方では政治活動の自由を過度に制約することのない、つまり立法事実に照らして必要最小限度と言えることが必要でありまして、これらのバランスに鑑みて各党各会派において政治的、政策的な御判断も踏まえて検討がされているものと承知しております。
以上です。
○高井委員
ありがとうございます。
有権解釈権がないということで、そういうお答えでいいと思うんですよ。だから、内閣法制局にもそういう答えをしてもらえませんかね。あくまでも国会が法律を決めるんだから国会議員に有権解釈権があるということかもしれませんけれども、しかし、それに法律的見地からいろいろなアドバイスをしてくださるのが衆議院法制局であり、内閣法制局だって、国会の場で正式に質問しているわけですから、そこはやはりちゃんと答えていただきたい。そうしないと、内閣法制局には本当にすばらしい人材が集まっているのに、政府から聞かれたことしか答えないとか、政府提出の法律にしか答えないというのはもったいなさ過ぎですので。是非、内閣法制局、あるいは国会全体として法改正が必要だということであれば、私は憲法を改正して憲法裁判所までつくらなくたってそのくらいはできると思うんですよ、だから提案しているので。これができないんだったら憲法裁判所をつくるしかないんですけれども、そんなことをしなくたって内閣法制局にすばらしい人材がいるんですから、是非これは国会としても検討していただきたいと思います。その上で、政治団体からの献金額が我々は少なければ少ないほどいいと。本来は禁止したいんですけれども、何度も言うように政治団体が抜け穴になっている可能性があるので、できる限り低くしたいと思うんですが。当初、維新は一千万円という案で、私たちは一千万でも生ぬるい、もっと厳しくすべきだと思っていますが、それが譲歩によって総枠六千万、個別制限二千万と大分後退してしまったんですけれども、これに対して、立憲民主党と維新の協議と聞いていますので、それぞれお答えください。
○大串(博)議員
ありがとうございます。
総枠制限と個別制限のところの話ですけれども、その他政治団体からその他政治団体へのところに関しては、元々五千万円というのがあって、維新さんは一千万円まで下げるべきだというのがありました。私たちは三千万円まで下げるのでどうだという、そういうスタンスだったんですね。様々な議論があった上で、個人の寄附の上限額と合わせて二千万円というところで落ちついたという経緯です。一方、その他団体から政党に対する寄附に関しても、性質としては個別制限で似通っているということから、同様の考えで二千万円としたということです。
総枠のところは、その他団体からその他団体へのところと、その他団体から政党への個別と二段階あります。二千万円、二千万円の上限。いわゆる政治団体全体のオペレーション活動が総枠なので、二千万円、二千万円ということを併せて考えると、規制の必要性と政治活動の自由度のバランスを取って六千万円とした、こういう経緯でございました。
○青柳(仁)議員
お答えいたします。
先ほども答弁を申し上げたんですけれども、維新の会としては運用としては全て禁止しているんですけれども、提出させていただいた法案は元々、憲法上の検討から一千万円ということにしておりました。ただ、その際にも、一千万円の根拠は何かという話は、実は様々な、憲法の学者さんですとか法制局を始め御指摘はありまして、我々は個人の低い方に合わせたんですけれども、法人に合わせるのであれば高い方の二千万に合わせるべきではないかとか、そもそも個人と団体とが一緒でいいのか、団体ならもう少し高くあるべきじゃないかというような御指摘もございましたので、そういったことも含めて検討したということでございます。
それからもう一つ、先ほど来から小泉委員の方からいろいろお言葉をいただいて大変恐縮ではあるんですが、我々は文書は重要だと思っているんですが、文書だけが重要だと思っているわけではありませんで、当然、企業、労働組合、職員団体その他の団体は、様々な方のおっしゃっていることであるとか文書も含めた中で、我々は三十年前からの約束として、ここは最後に残ってしまった抜け穴、これを禁止するべきだというふうに考えておりますし、三十年前からの宿題だというふうに捉えております。
そういった意味では、会社、労働組合、職員団体その他の団体から政党、政治資金団体に行く寄附の部分、ここを禁止することが本丸なんですね。ですから、まずはこれをしっかりとやること、これは全会派で一致をしたい。その上で、政治団体に関しては、自民党も含めた、れいわ新選組さんも含めた全会派がどういう基準であれば一致できるか、こういうことを幅広く考えていきたいと思っておりますし、出発点としての数字として考えたというところがあるということでございます。
○高井委員
青柳さんがさっき立法事実の話をされていましたけれども、確かに個人献金で政策をゆがめた立法事実はないかもしれませんが、政治団体が政策をゆがめた例は私は何度も経験しておりますので、間違いなく立法事実はありますので、私は、ここはしっかり限度額を設けるべきだという考えを述べておきます。
そこを一応塞ごうとしたのが、法案に二十二条の六の三というのを新たに追加して、タイトルでいうと雇用関係の不当利用等による寄附等の制限と。るる条文が書いてあるんですけれども、本当にこれで抜け穴にならないのかというのが我々には非常に疑問です。立法提出者、立憲さん、維新さん、有志さん、それぞれお答えください。
○本庄議員
高井委員にお答えいたします。
御指摘の条文については、罰則規定こそありませんけれども、ダミーの政治団体を介した迂回献金というまさに本条の禁止する核心的な部分と、本条の禁止規範としての趣旨は明確であることから、行為規範として十分に機能する法規範たり得るというふうに考えています。
さらには、迂回献金とまで評価できるかどうか悩ましいグレーな部分についても、行動準則として機能することにより、十分に抑止効果はあるというふうに考えています。 更につけ加えるならばですが、本法案においては、雇用関係の不当利用等による寄附の制限だけではなく、企業、団体から政治団体への寄附を完全に禁止したことで、政治団体間の寄附の原資としての企業・団体献金を遮断するとともに、政治団体による寄附について年間総額六千万、同一の政治団体に対して二千万円との上限規制を設けているところであって、これらの措置が相まって可能な限り抜け穴を塞ぐべく努力したところでございます。
○青柳(仁)議員
お答えします。
今、本庄委員から御答弁があったものと基本的な立場は同じであります。
今、高井委員の方からも御指摘がありましたとおり、今回は、労働組合であるとか企業、団体というものが不当な形で自身の影響力を使って政治団体を迂回させて献金することを禁止する条文を入れてございますので、この点、我々はこれでしっかりとそういったものを止められるというふうに考えておりますが、もし止められないという御見解があるようでしたら、そういった条文の部分をどう変更していくのか、修正するのかというのも各党各会派から御提案いただいて、柔軟にそれは、維新としては全てを禁止しても構わないと思っているわけですから、しっかりと議論させていただければと思っております。
○福島議員
答弁いたします。私もここが一番の迂回献金を防止するためのキーだと思っておりまして、国会議員法制局と私はあだ名がつけられておりますけれども、条文をいろいろ見て、直に罰則をつけるような規定というのは、やはり雇用関係の不当利用がどういうのが不当利用かと明確に書けないものですから困難だと思います。
ただ、抜け穴が心配だというのであれば、今、政治資金監視委員会、これができることになっていて、その細目はこれから法律で定めることになっておりますので、例えばそこの中で不当な扱いを受けたというのであれば、その不当な扱いを受けた人が申立てを委員会に行って、さらにその委員会が調査を行って、必要に応じて勧告とか、あるいは措置命令、措置命令に従わなかったら罰則というような、間接的な罰則を作るということも立法上可能であると思っておりますので、この法案はいずれ出てくる法案でありますから、そこの中でしっかりと議論していきたいというふうに思っています。
いずれにしても抜け穴は完全に防ぐということで、可能な限りの限界まで防ぐための措置を講じるべきであると考えております。
以上です。
○高井委員
時間なので終わりますが、この部分は非常に重要な論点だと思いますので引き続き議論、そして三月三十一日までに終わらなければ引き続きやる、それが国会議員の責務だと思っております。
以上です。終わります。