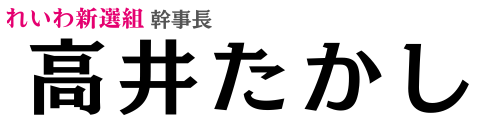【4月2日】財務金融委員会/日本の金融資産は1京円デフォルト確率は0.33%それでも日本は財政破綻する?

○井林委員長
次に、高井崇志君。
○高井委員
れいわ新選組の高井崇志でございます。
今日はIDA法改正ということで、IDAそれからIICへ国債での出資を可能とするという改正でありますが、これは、我々れいわ新選組は、国債は大いに発行すべきだ、まだまだ発行できるという立場でありますので、特に問題はございません。むしろ、予算委員会などの議論を聞いていると、国債発行は悪だ、これは政府もあるいは与野党共にそういう考え方で、国債発行するな競争のような議論が行われてきた。これは本当に残念な、誤った議論であると思いますので、今日はこの国債というものについて財務省の考えをお聞きしたいと思います。
まず、財務省がいろいろ国会で財政状況なんかを説明する際に、私は、債務残高の話しか、国債発行残高がとにかく一千兆円を超えて世界最悪の水準だ、GDPと比べた債務残高対GDP比は世界最悪の水準だという話しか聞いたことがないんですね。
資料でおつけしましたけれども、これは予算委員会でも同じ資料を見せたんですけれども、この国債の信認を測る指標というのは、この政府債務残高だけじゃなくて、ほかの指標もたくさんあるわけです。政府純利払い費とか、あるいは対外純資産のGDP比も大変重要な指標であるけれども、こういったものの説明が財務省からされたのは、私はちょっと聞いたことがないんですね。プライマリーバランスの話か債務残高の話しか聞いたことがありませんけれども。
これは事務方で結構ですが、財務省が財政状況を説明する際に、この債務残高対GDP比やプライマリーバランス以外の指標を使って説明したことはこれまでありますか。あるなら、いつ、何回ぐらいあるか、お答えください。
○吉野政府参考人
お答え申し上げます。
財政状況の説明に当たりまして、債務残高対GDP比やプライマリーバランス以外の指標をこれまで何回用いたかとのお尋ねについて、網羅的にお答えすることは困難でございますけれども、例えば、今通常国会におきまして、純債務残高対GDP比や利払い費といった指標を用いて財務省から我が国の財政状況について説明した実績は、現にございます。
網羅的にお答えすることは、繰り返しで申し訳ありません、困難でございますけれども、純債務残高対GDP比については少なくとも一回、利払い費については少なくとも二回、言及していると認識しております。
○高井委員
今日は時間がないので、どんな説明だったか、また今度聞きたいと思いますが、恐らく、私の記憶している限りでは、質問に答える形で、例えば政府純利払い費の対GDP比の数字は先進国で比べれば何位ですとか、そういう何か事実の説明であって、この指標を基に、財政状況がだからどうなんだというような説明を私はしていないんじゃないかと思いますので、これは、後でまた議事録を調べて、事務方に聞いて、また次の機会に質問したいと思います。
これは財務大臣にお聞きしますが、この資料にもつけたように、確かに、債務残高対GDP比を比べれば、G7の中では七位、一番下なんですね。しかし、ほかの指標を見れば一位か二位か三位で、特に重要な政府純利払い費は三位と書いていますが、最新の数字では、これは吉野次長が二位だというふうに答弁しているのを私は見ました。なので、最新の数字は二位なんですよ。つまり一位か二位。
つまり、G7の中でも非常に優等生である、ほかの指標を見ればということを、もっと財務省はきちんと公平に説明をすべきではないかと思いますが、財務大臣、いかがですか。
○加藤国務大臣
今お話があった債務残高GDP比を用いたり、あるいはプライマリーバランスを用いて財政経済運営というものを見てきている、それは、実際、これまでもそういった指標をもって見ていくということが決められているわけでありますから、我々はそれに沿ってお示しをさせていただいているということであります。
その上で、委員がお示しをされた指標というのも確かに指標としてはあると思いますけれども、それぞれが、前回も説明しましたので一個一個申し上げませんけれども、例えば、それが国ではなくて民間部門の話であったり、海外の動向等と国内の動向等によって大きく変わるものであったりということでありまして、そういった意味において、どういった指標をもって我が国の財政状況を考えていくべきなのか、そういったこれまでの議論の中で、私どもとしては、債務残高対GDP比又はプライマリーバランス、これを見ながら経済財政運営を行い、また、それを説明させていただいている、こういう経緯であります。
○高井委員
この二つ、債務残高とプライマリーバランスに私は本当に一方的に偏っていると思いますし、それはやはり、財務省として、財政再建をとにかく進めたい、国債をこれ以上発行させたくないということで、自分たちに都合のいい指標を声高に主張しているんだと私は考えますので、ここはまた議論をしていきたいと思います。
次に、資料二ですが、これも予算委員会で示した資料なんですが、確かに、国、地方の債務残高を見れば一千二百八十兆円と多いんですけれども、これは江田委員もよく使われている数字ですけれども、国の金融資産を見れば九千八百九十五兆円、それから個人の金融資産は二千百七十九兆円等々、こういった、つまり資産があるということをやはり見て、見比べるべきであると。
これは、ちょっと分かりやすい例で言うと、企業もそうですよね、借金している企業というのは、じゃ、それは危ない企業なのかといえば、決してそうではない。例えば、有利子負債の上位五社はどこかというと、一位トヨタ自動車、二位ソフトバンク、三位NTT、四位本田技研、五位三菱キャピタルですよ。トヨタなんかは二十九兆円、ソフトバンクも十九兆円、有利子負債があります。そして、上位二十社のうち六割は年商以上の負債がありますけれども、全く問題がない。それはやはり、それだけの資産あるいは企業としての価値、能力があるから借金できるわけですから、これは、私は、日本が負債残高が多いからといってそれが直ちに問題だということにならない一つの例だと。
もちろん、企業と政府は違うし、むしろ、でも、政府の方が通貨を発行できるんだから、より企業よりも考えなくてもいいことであるにもかかわらず、債務残高が多いということを財務大臣は声高に言われますけれども、今の私の考え、財政破綻する心配なんか、日本はこういった試算の数字を見ればないのではないですか。いかがですか。
○加藤国務大臣
必ずしも企業と国家というのは、いろいろな意味で、今委員の言われたことも含めて、単純に比較はできないんだろうと思いますし、企業においても、有利子負債が多ければいいというわけではなくて、それがきちんとした収益につながってきているということ、こういったことが大事なんだろうと思います。
国においては、先ほど申し上げたように、債務残高ということも含めて、例えばGDP比で見る、こういったところで我々判断をしてきているところでございますので、引き続き、大事なことはやはり市場における信認ということだと思います。
現時点では、これだけの国債残高を持ちながら、そしてこれだけの国債を発行しながらも、それが円滑に消化できてきているというのには、一つは、例えば家計の金融資産などが豊富にあるといったことも指摘をされていると承知をしておりますが、引き続き市場での信認を得るべくやはり努力をしていかなければ、一たびそれが崩れますと、金利の急上昇や過度なインフレが生じ、日本経済、社会に多大な影響を与える可能性も否定できないわけでありますので、我々としては、そういったことを念頭に置きながら、しかし他方で、財政に求められる役割は状況状況によっていろいろあります、それにもしっかり当然応えていくという中で、現時点においては、経済再生と財政の健全化、この両立を図るべく努力をさせていただいているところでございます。
○高井委員
今大臣がおっしゃったように、市場における信認が大事なわけですけれども、市場における信認が十分あるんじゃないかということを今申し上げ、大臣も、個人の金融資産が多いということがその一因になっていると。
だから、私が申し上げているのは、過度に恐れ過ぎなんじゃないですか、心配だ心配だと言ってあおって、もう国債をこれ以上発行できないんだというようなことを言い過ぎるのはよくないと申し上げています。
客観的な市場の信認というのが出ているのが、その次の資料です。資料三、CDS、クレジット・デフォルト・スワップから算出した五年以内の国債デフォルト確率、これも江田委員がよく取り上げていますけれども、これは、G7で比べただけでも、日本はドイツに次いで二番目にいい。〇・三三%ですよ。限りなくゼロに近い。イタリアは二・四だし、例えばトルコとかブラジルなんかは、もう一〇を超えている国もあるわけですよ。
こういった市場がまさに判断した数字が日本はこれだけいいわけですけれども、じゃ、大臣、何で日本はこんなに低い、〇・三三%という低い比率なのか、その理由はどう考えていますか。
○加藤国務大臣
このお示しをされた数字は、ちょっと小さい字で見えないんですけれども、第一生命経済研究所ですか、ここが試算された数字ということで、ちょっとこれに対して政府としてコメントするというのは控えたいと思いますが、ただ、この背景にあるのはCDSだろうというふうに思います、一つの要素だと思います。
CDSというのは、御承知のとおり、買手が売手に対して保証料を支払う代わりに、国がデフォルトしたときに損失の保証を受けるものであり、いわば損失保証料率ということを認識をしているところでございます。
そうした損失保証料率が低いという背景としては、潤沢な家計、金融機関や経常収支の黒字等を背景に、先ほど申し上げたように、国債が国内で安定的に消化されるという状況の中で、財務健全化目標を掲げ、その取組を進めてきたことによって市場からの信認を維持してきた、こういったことがあると考えておりますので、引き続きそうした信認が得られるように努力をしていきたいと思っております。
なお、CDSの分析に当たっては、CDSそのものの取引量が少なく取引主体が限られている、こういった点にも留意する必要があるという指摘があるということも認識をしているところでございます。
○高井委員
これは経団連のシンクタンクのレポートでもありますし、江田委員もこの数字を出していますので、是非これは加味していただきたい。
それから、最後に質問します。
国債償還費、これが財政を圧迫していること、水増ししている原因だと何度も主張していますが、これをなぜ計上しているのか。それから、これは世界各国と同じように、国債償還費を計上するのはやめるべきじゃないですか。二問まとめて、最後に財務大臣、お答えください。
○井林委員長
申合せの時間が経過しました。簡潔にお願いいたします。
○加藤国務大臣
債務償還費は、国債の償還財源を確実に確保しつつ、償還のための財政負担を平準化するという観点から、六十年償還ルールの下で、法律の規定に基づいて計上しているものでありまして、このルールそのものは財政健全化の精神を体現するものとして定着していること、また、多くの国民の方々に負担していただいている税金等で成り立つ一般会計において債務返済の負担の具体的な額を明らかにすることは、債務の負担の見える化の意味でも有意義だと考えております。
確かに、こうした計上を行っているというのは、先進国の中でというか、日本だけという御指摘は確かにありますが、しかし、他国において、六十年償還ルールのような償還財源の確保に関して毎年度適用される特別の制度はないものの、財政規律維持に関する基準等を法律において規定をしており、また、実際の債務残高対GDP比も日本よりはるかに低い水準にあるものと承知をしておりまして、こうした財政規律維持に関する枠組み全体や、債務残高GDP比の動向も見て検討する必要があろうと考えております。
○高井委員
終わりますが、引き続きこの話は議論していきたいと思います。
ありがとうございます。